2025.07.11
INDEX
動画マニュアルとは、業務手順や作業方法を動画で説明するマニュアルのこと。
特に製造業では、視覚的に工程を理解できるため、文章や図だけのマニュアルよりも理解が早く、ミスの削減にもつながります。
従来の紙マニュアルでは、工程の細かな動きやタイミングを正確に伝えるのが難しく、習得に時間がかかるという課題がありました。しかし、動画であれば、作業手順を実際の映像で確認できるため、直感的に理解しやすくなります。また、音声や字幕で補足説明を加えることで、さらに伝達力が向上します。
たとえば、ある製造ラインでは新人教育に動画マニュアルを導入した結果、従来の半分の時間で基本作業を習得できるようになりました。しかも、映像を繰り返し見られるため、自主学習のツールとしても活用可能。
このように、動画マニュアルは製造現場の教育効率を高め、品質や安全性の向上に直結します。
製造現場では、日々の作業を正確かつ効率的にこなすことが求められます。
そんな中で注目されているのが、動画マニュアルの活用。
紙や口頭だけで伝えていた手順を、動画にすることで「誰でも同じように」「何度でも」学べるようになります。
ここでは、製造業で動画マニュアルを導入するメリットについて見ていきましょう。
動画マニュアルを使えば、新人教育にかかる手間とコストを大きく減らすことができます。
一度作った動画を何度でも使い回せるからです。
実際、ある工場では、動画マニュアルによって教育担当者の作業時間が半分以下になり、その分現場の生産性も上がりました。時間や場所に縛られず視聴できるため、スキマ時間での学習も可能になります。
このように、教育の効率化とコスト削減を同時に実現できるのが、動画マニュアルの強みです。
動画マニュアルを導入すれば、作業手順のばらつきをなくし、品質の安定化につなげることができます。視覚情報によって誰でも同じ作業が再現できるためです。
たとえば、複数の作業チームが同じ工程を動画で確認することで、やり方が統一され、不良品の発生率が下がったという事例もあります。
つまり、動画は「正しいやり方」を見える化することで、現場全体の品質を高める手助けになるのです。
言語や経験に関係なく、誰でも作業内容を理解しやすいのが動画マニュアルの大きなメリットです。理由は、視覚で直感的に覚えられるからです。
たとえば、外国人スタッフに日本語で説明しても伝わりにくかった工程も、動画に字幕や多言語音声を加えることで理解度が格段に上がったという声があります。
動画は、言葉の壁を越えて「見て覚える」ことを可能にし、教育の質を大きく引き上げてくれます。
ベテランの技術やノウハウを「見える形」で残すことで、属人化を防ぐことができます。動画にすることで、その人だけが持っていたやり方が共有財産になるからです。
たとえば、退職予定の熟練者の作業を動画で記録した現場では、その後も新人が同じクオリティで作業を再現できるようになりました。
技術の継承がスムーズに進むことで、現場の安定性と生産性も維持されます。動画は知識を“人に頼らず”伝えるための強力な手段です。
動画マニュアルは、教育や技術継承だけでなく、現場のさまざまな業務で活用されています。実際の現場では、作業の手順共有や保守作業の記録、安全教育など、幅広い用途で効果を発揮しています。
紙や口頭では伝えにくかった動きやタイミングも、動画なら簡単に理解できるため、ミスの削減や習熟時間の短縮にもつながります。ここでは、製造業の現場で実際に活用されている具体例を3つ紹介します。
動画マニュアルを使えば、製造ラインの作業手順を全員で正確に共有することができます。なぜなら、映像によって「どう動くか」をそのまま見せることができるからです。
たとえば、ある部品組立工場では、ラインごとにやり方に微妙な違いがあり、不良品や作業ミスが頻発していました。そこで動画で標準作業を記録・共有したところ、作業が統一されてトラブルが激減。新人も短期間で即戦力になったと言います。
作業のばらつきをなくし、誰でも同じクオリティで作業できるようにするために、動画は非常に有効です。
設備の保守やメンテナンスの手順を動画で残しておくことで、技術の引き継ぎがスムーズになります。理由は、細かな作業や注意点を映像でそのまま記録できるからです。
例えば、ある製造設備では、月に一度の分解清掃の方法が担当者ごとに曖昧になっており、作業ミスが発生していました。そこでベテランの作業を動画で記録し、新人にもその映像を見せながら教育を行ったところ、作業時間が短縮され、トラブルも減少しました。
このように、メンテナンス作業の“見える化”は、効率だけでなく安全性の向上にもつながります。
安全教育や災害対策のトレーニングにも、動画はとても効果的です。理由は、実際の危険場面を疑似体験できることで、理解と記憶に残りやすくなるからです。
例えば、火災時の初期対応や機械への巻き込まれ事故の注意点などを、動画でシミュレーション形式にしたことで、従業員の危機意識が高まり、ヒヤリ・ハットの件数が減少したというケースもあります。
言葉だけでは伝わりにくい“もしもの時の行動”を、動画ならリアルに伝えられます。教育効果を高めるだけでなく、職場の安全文化づくりにもつながります。
動画マニュアルを作るには、「自社で作る」か「外部に依頼する」かの二択があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、目的や社内リソースによって適した方法は変わります。
社内に制作スキルや時間があるなら内製も選択肢になりますし、クオリティや効率を重視するなら専門会社に頼むのも有効です。ここでは、それぞれの方法の特徴と選び方のポイントを見ていきましょう。
自社で動画マニュアルを作成すれば、現場のリアルなノウハウをスピーディーに反映できます。現場をよく知っている人が関わるため、内容に無駄がなく、実用的なマニュアルに仕上がるのがメリットです。
たとえば、スマホや簡単な編集ソフトを使って自分たちで撮影・編集することで、コストも最小限に抑えられます。また、修正や更新も自分たちのペースで対応できるため、変化の早い現場にフィットします。
ただし、撮影や編集のノウハウが必要だったり、品質にバラつきが出たりする点には注意が必要です。小規模で手軽に始めたい場合には、自社制作が現実的な選択肢になります。
品質や完成度を重視するなら、動画マニュアル制作の専門会社に依頼するのがおすすめです。プロに任せることで、撮影・編集・構成まですべて高水準で仕上がるからです。
たとえば、アニメーションやナレーションを入れて、視覚的にわかりやすい構成にしてくれる会社も多く、社内では対応できない部分までカバーしてくれます。また、マニュアル制作に慣れたスタッフがサポートしてくれるため、業務内容を整理しながら制作を進められるのも利点です。
そのぶんコストはかかりますが、「誰が見ても伝わるマニュアル」を作りたい場合には、費用以上の効果が期待できます。
動画マニュアルを効果的に活用するには、「ただ撮るだけ」では不十分です。視聴する人にとってわかりやすく、伝わりやすい内容にするためには、準備から撮影・編集まで、いくつかの大事なポイントを押さえておく必要があります。
とくに、目的の明確化、構成の工夫、現場での撮影ノウハウは、マニュアルの完成度を大きく左右します。ここでは、初めてでも失敗しにくい動画マニュアル制作の基本的な流れと注意点を紹介します。
動画マニュアルを作る前に、何より大切なのは「目的」と「対象」を明確にすることです。何のために作るのか、誰に見てもらいたいのかがハッキリしていないと、伝わりにくい動画になってしまいます。
たとえば、「新人向けに初期作業を覚えてもらう動画」なのか、「ベテラン向けのトラブル対応マニュアル」なのかで、構成や内容はまったく変わってきます。
また、動画の全体構成もこの段階で考えておくとスムーズです。導入 → 手順 → 注意点 → まとめ、といった流れを設計しておくことで、視聴者が迷わず内容を理解できるようになります。
この準備がしっかりしていると、撮影や編集の工程もぶれずに進み、完成度の高い動画になります。
わかりやすい動画を作るには、事前の台本(シナリオ)作りが欠かせません。なぜなら、流れやセリフが曖昧なままだと、撮影が進まなかったり、伝わりにくい動画になったりするからです。
たとえば、現場の作業工程をそのまま撮影する場合でも、「どこで説明を入れるか」「どのタイミングでポイントを見せるか」を台本にまとめておけば、無駄なく効率的に進められます。
また、話し方やセリフも整理しておくことで、聞き取りやすく、理解しやすい動画になります。とくにナレーションを入れる場合は、専門用語の言い換えや補足説明も意識しましょう。
「現場の経験をそのまま映す」だけでなく、「伝えるために整理する」ことが大切です。
撮影時には、見え方や聞こえ方に注意することで、完成した動画のクオリティが大きく変わります。結論から言えば、「映像と音声のわかりやすさ」が最も重要です。
たとえば、カメラのアングルが悪くて手元が見えなかったり、周囲の音が大きすぎて声が聞こえなかったりすると、それだけで内容が伝わりにくくなります。また、作業者の動きに合わせてカメラを動かすなど、視聴者が「どこを見ればいいか」がわかるような撮影が求められます。
撮影場所の明るさや背景の整理、音声の録り方など、ちょっとした工夫で動画の印象がぐっと良くなります。現場のリアルさは残しつつ、見やすさ・聞きやすさを最優先に考えましょう。
動画マニュアルには多くのメリットがありますが、導入前に知っておくべき注意点もあります。すべてが便利というわけではなく、導入・運用には一定のハードルがあるため、事前に理解しておくことが大切です。
特に「初期コスト」と「更新管理」の2点は、多くの現場でつまずきやすいポイントです。これらを踏まえて準備することで、導入後のトラブルや無駄な負担を防ぐことができます。
動画マニュアルの制作には、ある程度の初期コストがかかります。特に外部に依頼する場合は、撮影機材・編集・ナレーションなどがセットになっているため、想定以上に費用が膨らむこともあります。
たとえば、クオリティの高い動画を作るには数十万円以上の予算が必要になるケースも少なくありません。一方で、内製すればコストは抑えられますが、そのぶん社内の時間と労力が必要です。
導入前には、予算だけでなく、目的に対して「どれくらいの投資価値があるか」をしっかり見極めることが大切です。
動画マニュアルは一度作ったら終わりではなく、内容の更新も重要なポイントです。現場の手順やルールが変わったときに、マニュアルもあわせて更新しないと、誤った情報が広まってしまうリスクがあります。
たとえば、設備が変わったのに古い手順のまま動画を使い続けた結果、ミスが発生してしまったという事例もあります。特に製造現場では、工程の変更や改善が日常的に行われるため、定期的な見直しが欠かせません。
更新しやすい体制をつくっておくことで、動画マニュアルを長く・正確に活用することができます。
動画マニュアルの制作をプロに任せたいとお考えなら、株式会社テックスにご相談ください。製造業の現場に特化した動画マニュアル制作を数多く手がけてきた当社だからこそ、実務に即した、わかりやすく使いやすいマニュアルを提供できます。
テックスでは、構成設計から撮影・編集・ナレーションまでを一貫してサポート。お客様の業務内容に合わせて、オーダーメイドで最適なマニュアルをご提案いたします。
「どこから始めればいいかわからない」「短期間で仕上げたい」「まずは1本だけ試してみたい」など、どんなご相談でも大歓迎です。ぜひ一度、お気軽にお問い合わせください。現場を変える第一歩を、私たちと一緒に踏み出しましょう。
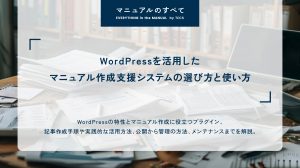
INDEXなぜオンラインマニュアルにWordPressを選ぶべきか?WordPressの概要とCMSとしての強み使いやすさ柔軟性コミュニティサポートなぜマニュアル作成にWordPr...
取扱説明書などのマニュアル類の制作や、世界40ヶ国語に対応する多言語翻訳、Webページ/Webマニュアルの制作、
カタログ・パンフレットなどの販促物の制作、CGを駆使した製品紹介動画の制作など。
産業機器から家電製品まで技術に強いドキュメンテーション制作会社です。

INDEXおすすめのマニュアル制作会社比較表マニュアル制作会社とは?マニュアル制作会社の費用相場マニュアル制作会社を選ぶ際のポイント対応可能なマニュアルの種類を確認する制作実績を確...
マニュアル制作会社のおすすめ5選!選ぶ際のポイントや注意点を詳しく解説

INDEXマニュアル動画とは?マニュアル動画の作り方目的を明確にする②動画の構成・台本を作成する③撮影を行う④編集する⑤動画を公開・共有するマニュアル動画の活用例動画のマニュアルが...
マニュアル動画の作り方を解説!活用例や制作におすすめのツールもあわせて紹介

INDEX動画マニュアルとは?製造業で動画マニュアルを導入するメリット教育コストの削減作業の標準化・品質向上 外国人作業者や新人でもわかりやすい属人化の防止・ナレッジの可視化製造業...
動画マニュアルは製造業で作成する?導入するメリットや活用事例を解説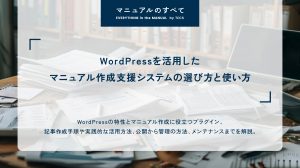
INDEXなぜオンラインマニュアルにWordPressを選ぶべきか?WordPressの概要とCMSとしての強み使いやすさ柔軟性コミュニティサポートなぜマニュアル作成にWordPr...

1
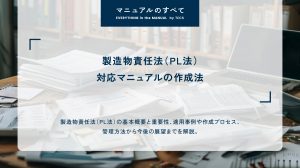
INDEX1. 製造物責任法(PL法)対応マニュアルの作成法とは製造物責任法(PL法)とはPL法対応マニュアルの重要性2. 製造物責任法(PL法)の基本概要PL法の目的と施行背景製...
製造物責任法(PL法)対応マニュアルの作成法2
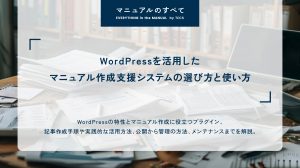
INDEXなぜオンラインマニュアルにWordPressを選ぶべきか?WordPressの概要とCMSとしての強み使いやすさ柔軟性コミュニティサポートなぜマニュアル作成にWordPr...
WordPressを活用したマニュアル作成支援システムの選び方と使い方3
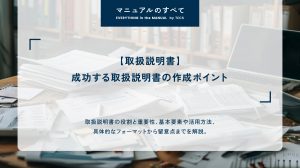
INDEX取扱説明書の役割と重要性読者目線での設計の重要性2. 取扱説明書の基本要素読者目線での構成と流れ明確な見出しと構造化された情報簡潔で平易な言葉遣い3. 視覚的要素の活用図...
【取扱説明書】成功する取扱説明書の作成ポイント